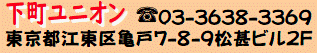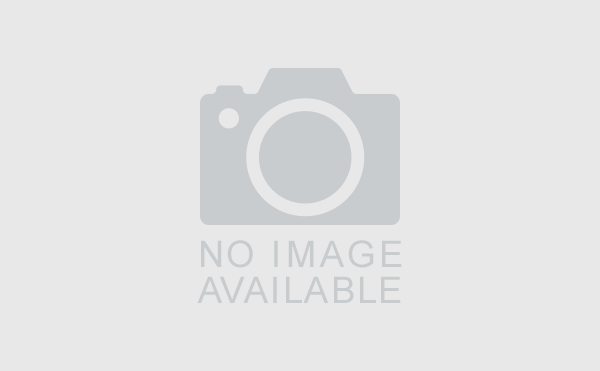最低賃金ものがたり 8
最低賃金はどのように決まるのか その⑤
納得のいく指標とは?
厚生労働省に聞いてみた!
前回、EUが賃金の「中央値」の6割を、最低賃金の指標としていることについて述べました。日本政府の公式資料での賃金の中央値もお伝えしたかったのですが、どうしても見つからなかったため、厚生労働省に直接電話して、聞いてみました。
厚労省に電話してわかったことは、賃金の中央値は、ナント、厚労省として算出はしているが公表はしていない、必要なら図表から割り出して下さい、ということでした!厚労省がこのような基礎的データを公表しないで、最低賃金の引き上げという大きな目標にむかって、社会に理解を広めていく責任をまっとうしているといえるのでしょうか。算出した賃金の中央値については、誰でも簡単にみられるように公表することを要望して、電話を終えました。
さて、厚生労働省発表の資料「都道府県別の一般労働者の賃金中央値に占める最低賃金額の割合(2024年)」によると、賃金の中央値の母数について所定内給与のみとして、賞与などは含まれていません。元々最低賃金は賞与等は含めないのですが、実際には主に企業規模や正規/非正規雇用労働者の間の賃金の大きな格差の原因として、賞与の有無や金額による影響は大きいといえます。母数に賞与を入れるかどうかで中央値に占める最低賃金の割合も大きく変わります。厚労省では、この資料を作成したのも今年が初めてとのことでした。
高知県にも聞いてみた!
一方、今回の改定で、高知県が全国に先駆けて「中央値の6割」を最低賃金の金額決定にあたっての指標の一つとして導入を決めました。自治体として最低賃金について真摯な議論をしていることに、希望を感じました。高知県の労働局にも電話して聞いてみました。
各都道府県での最低賃金の審議会では、中央審議会の目安額を参照しながらの議論が長年続いてきましたが、独自の判断を示す自治体が出てきています。昨年は徳島が80円以上という大幅な引き上げを打ち出し「徳島ショック」という言葉まで出ました。今年は高知が「中央値の6割」を2年後の目標とすることを打ち出しました。これは賃金の中央値を最低賃金の金額の指標として打ち出した初の試みとなります。なお、高知県の担当者に確認したところ、この中央値には賞与なども含めて計算しているとのことでした。理由は賞与も皆さん生活費に充てているから、ということでした。やっぱり、そうですよね…。
高知県が明確なデータに基づく客観的指標を打ち出したことの意義は、端緒についたばかりとはいえ、とても大きいものがあります。客観性は、公労使三者の納得感をつくる素地になるからです。また、最低賃金が、中央値の6割=相対的貧困線(これを下回ると社会的な貧困層とみなす)を下回るような金額であってはならないという国際標準を再確認したことにもなります。そして近年形骸化が露わになってきていたランク別の「目安方式」に対して、別の視点を立てたことになります。 日本の最低賃金を、金額と基準の双方から国際的なスタンダードに近づけていくことが、求められています。(前田)