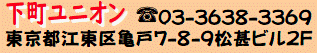最低賃金ものがたり 6
下町ユニオンニュース 2025年7月号より

最低賃金はどのように決まるのかその③
「生計費」は実態にあっているのか?
前回地域別最低賃金の決定にあたり考慮すべき3要素は、「地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力」とされています。今回は「生計費」について考えてみたいと思います。
生活費がいくらかかるのかを踏まえて地域別最低賃金の金額が検討されるわけですが、そのサンプルとなる生計費は、果たしてどこまで実態に見合ったものとなっているのでしょうか。
目安委員会で参考とされる各都道府県ごとの生計費は、2つの点で疑問があります。一つには、大都市圏とその他の地域での生計費の差額が、大きすぎるのではないかということです。これは多くの研究者等から指摘がされていることです。
生計費の中で大きな比重を占める住宅費(家賃)は、確かに都市圏が高い傾向があります。しかし食費などに地域ごとの違いはほとんどありません。また、都市圏では、例えば交通費は、公共交通の発達など社会的インフラがあるために個人で大きな支出をしなくても済みますが、車が不可欠な地域では、車の維持費や燃料代に、相当のお金が必要です。
そうしたことを考えると、生活にかかるお金の「総額」で考えれば、都市圏と地方で大きな違いはなく、少なくとも地域別最低賃金の金額に示される程の生計費の違いはない、ということが言えるのです。
加えて、お米やパン、菓子をはじめ飲食料品のこの三年間での値上がりはすさまじいものがありますが、生計費に十分考慮されているとは思えません。
そして2つ目に、より根の深い問題があります。それは最低賃金で働く人をどのような労働者として見ているか、ということです。生計費のサンプルも、若年単身者モデルがずっと使われてきました。しかし「ワーキングプア」という言葉がすっかり定着しているように、最低賃金の金額の近辺の賃金で働く人が圧倒的に増えているのが現状です。最低賃金の引き上げを一番必要としている非正規雇用で働く人は、一人暮らしの若者だけではありません。シングルマザーで働く人の半分以上が非正規雇用です。
家計を主に支える人が他にいて最低賃金で働く人は生計の補助労働、という従来の視点そのものが、いつまでたっても上がらない最低賃金を、維持してきてしまったのではないでしょうか。ILOの131号条約、135号勧告では、最低賃金について、「労働者と家族の必要を満たすこと」を求めていて、日本も50年以上前に批准しています。日本は、最低賃金の基準について、守らなければならない国際的な約束を無視し続けてきたことになります。 最低賃金を検討する際の参考となる生計費について、根本的な見直しがはかられるべきではないでしょうか。(K.M)