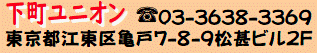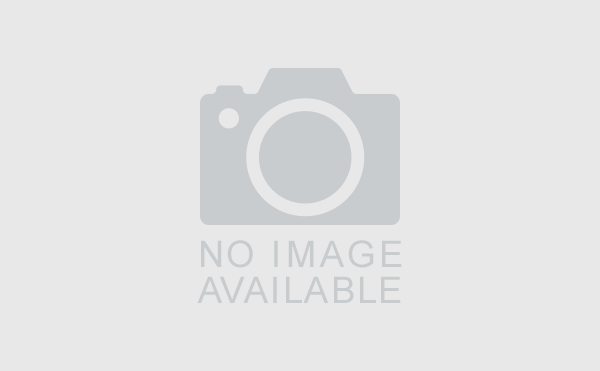人間らしく働き生活できる社会はどこに? ~厚労省の研究会の報告書について~
下町ユニオンニュース 2025年2月号より

今年1月、厚労省が設置した「労働基準関係法制研究会」(以下、研究会)が報告書をまとめました。労働基準法や労働安全衛生法など労働に関する法制度の見直しを目的として、一年間の議論をまとめたものです。委員は10人。全員が学者で、労働組合の関係者は一人もいません。
🔵国が労働者の人権を保障する責任を負う、という視点がない、新自由主義的な内容
報告書では、すべての労働者の心身の健康を守るという視点が大事だと書かれています。しかし、報告書の中では、労働者の生活や権利を守るために国がいま何をすべきなのか、現在の労働行政に問題はないのか、といった検討がまったくありません。労働者を守るために国が果たすべき役割、責任といった視点が抜け落ちています。
その一方で、労使の合意によって「法定基準の調整・代替」を行う仕組みが重要だと指摘し、そのために職場の過半数代表を強化して、労使コミュニケーションを活性化することが重要だと繰り返し指摘します。つまり、各企業での労使の合意によって最低基準を下回る労働条件を設定して良い、ということになりかねない話です。確かに労使の合意は重要です。しかし、最低基準を下回ることまで容認するような議論は間違いです。
また、労働組合の活性化が大事と言いつつ、労働組合つぶしや不当労働行為が横行している労働現場の状況等には一切触れていません。
要するに、国の責任をどんどん小さくし、問題を労働現場に丸投げするような提言です。新自由主義の自己責任論や規制緩和の議論と同じ構図だと感じます。
🔵フリーランスの権利保障や長時間労働の規制強化には踏み込まず
報告書では、フリーランスの人々と労働法との関係についても検討しています。諸外国ではフリーランスとして働く人々の権利を守るために、そうした人々が労働法の対象として認められやすくなる取り組みが進んでいます。しかし、今回の報告書では、引き続き検討を行うべきとして、そうした議論を先送りしました。
また、長時間労働の規制を強化する議論はあっさりスルーして検討せず、その一方で、テレワークでの「みなし労働時間制」の導入や、副業・兼業での割増賃金の廃止など、長時間労働を助長するような危険な提言を出しています。
また、労働時間の情報公開、勤務間インターバルの導入、つながらない権利(企業が労働者にメール・SNSなどで連絡を取る時間を制限する)などの点も議論されました。しかし、積極的な提言にはなっていません。労働者を守るために規制を強化する、という姿勢が感じられません。
🔵報告書の議論に欠けているもの
この報告書の最大の問題は、労働者の約4割におよぶ非正規労働者(その多くが女性です)の処遇改善、ジェンダー差別の撤廃、外国人労働者や高齢労働者の人権保障、拡大する日雇い労働(スキマバイト)と貧困など、今の労働現場で苦しんでいる人々の問題に、まったく言及していないことです。
現在の労働法制の表面をなぞっただけの検討で、経団連など財界の意向にはしっかり気を配る。そんな姿勢だけは伝わってきます。 厚労省の労働政策審議会が1月21日に開催、この報告書が報告され議論が始まりました。現場の声を無視する議論が進まないよう、労働者の生活と権利を守れ! という声を強く挙げていく必要があります。(A)